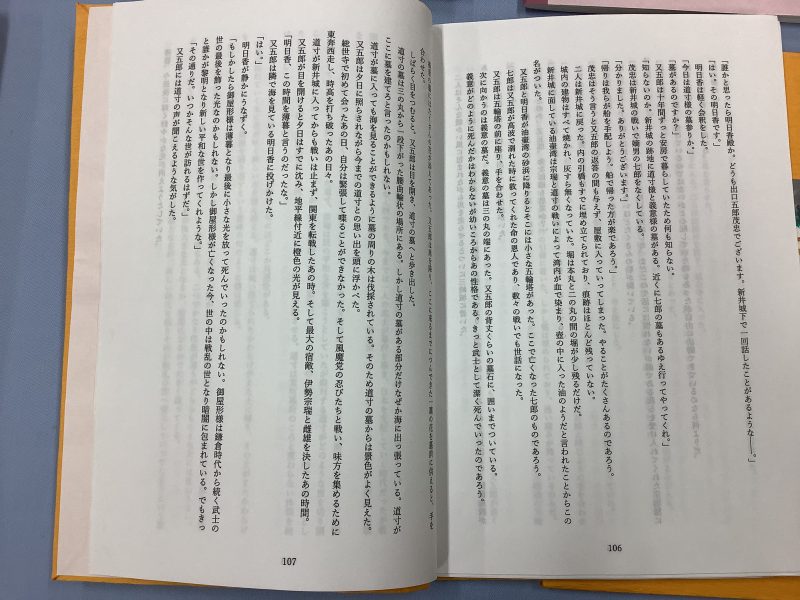国語科
薄暮 ~三浦家盛衰記~
2年S.S君
僕は今まで書くことが嫌いだった。 小学生の頃に出された作文の課題は憂鬱で仕方がない。 何時間考えても鉛筆は動かず、 作文を書けませんどうしましょうという作文を書いたほどだ。 しかしそれが変わったのは普通部に入ってからである。
中学一年生の二学期。 国語の授業でエッセイを書く課題が出た。 縛りは特になく、 何を書いてもいいという。 僕は作文用紙と対面したがいつものように手が動かない。 しかし良い案が頭に降りてきた途端、 今度はシャーペンを持つ僕の手が止まらなくなった。 自分の手ではないように感じた。 しかしこの三十分間はとても楽しく、 頭のどこから出てきているのかもわからない巧みなアイデアが次々と出て来たときは今まで感じたことのない快感を覚えた。 ここで僕は初めて書く楽しさを知ったのである。
そして僕は生粋の歴史小説好きだ。 五十冊以上は読んでいるだろう。 僕が初めて歴史小説と出会ったのは小学五年生の頃。 僕が本屋にふらっと立ち寄ったとき、 一冊の本が僕の前に現れた。 安部龍太郎さんの 「冬を待つ城」 という歴史小説である。 僕は城に興味があったためタイトルに惹かれ、 気が付くとレジに向かっていた。 しかし買ってはみたものの初めての歴史小説だったこともあり、 言葉遣いや人間関係が難しく読むのに時間がかかった。 しかも六百ページに及ぶ長編である。 本屋に行ったのが十一月だったが読み終わった頃には三月になっていた。 冬を待つどころか通り過ごしてしまったようだ。 しかしその後、 様々な歴史小説を読んでいくうちにその魅力に引き込まれていった。 歴史小説の醍醐味は実在していた昔の人の人生に自分の人生を重ねあわせ、 彼らの失敗や成功から自分を見つめ直すことができる点にあるだろう。 他にも魅力は沢山あるのだがこれ以上話すと長くなってしまうので、 そろそろ労作展の話に移るとしよう。
僕が本文を書き始めたのは期末試験が終わってからなのだがどんなに時間をかけても全くページは進まなく、 七月中旬になってもまだ二十ページほどしか書けていなかった。 しかしその原因はすぐに分かった。 セリフだらけなのだ。 今まで書いた文章を見ると、 八割がセリフだったのである。 これではドラマの台本と同じようなものだ。 ここで僕はセリフとセリフの間に地の文を入れることにした。 地の文とは会話文以外の文章で状態を説明する文である。 しかし出来上がっている文章に新たな文を入れるのは難しい。 そこで僕は頭の中でその場面の状況を想像することにした。 そのページの内容をドラマのように頭の中で再現することで人物の服装や表情、 場の雰囲気や建物、 気象までが言葉で表現しやすくなるのである。 そもそも小説は読者に想像させる文学だ。 漫画やアニメは視覚で観るものだが、 小説は頭の中に場面を描いて読むものである。 少なくとも僕はそうやっていつも小説を読んでいる。 この方法は最後まで役立ち、 僕の小説をより一層濃いものとした。
しかし、 ときにはこの方法が通用しない事もある。 「書けても一日に十ページ。」 そんな辛い日が続いた。 しかし僕がパソコンと向き合わなかった日は無かった。 それは小説を書くことが楽しかったからであろう。 一日五ページほどしか進まなくてもそれが途切れることはなかった。 それが結果的に三百ページに及ぶ小説の完成につながったのである。
今年の労作展は僕に新たな場を与えてくれた。 小説を書くという新たな能力、 そしてその楽しさ。 それらを教えてくれたのは労作展だった。 どんなに大変なことでも改善策を見つけながらコツコツと毎日続ければ大きなものになるということ。 そして好きなことをこれからも伸ばし続け、 止めないこと。 そんなことを学ぶことができた労作展だった気がする。
僕の小説につけられた賞の札を見たその時、 僕は思った。