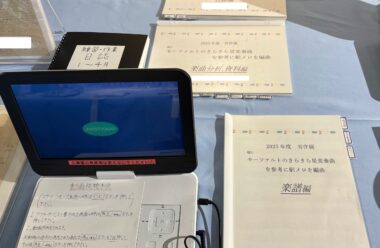音楽科
「音楽」をした
1年K.W.君
僕は労作展の装飾係だった。クラスメイトの作品を並び終えた後「いよいよ労作展が始まる。」と感慨深く思った。五月から僕の頭の中の大部分は労作展のことで占められていた。途中、テスト期間中は一旦、意識しないようにしていたが、終わったら労作展のことを考える日々がまた始まった。だから、装飾係の仕事を終えた時に「その生活がようやく終わるんだ。」と僕は清々しい気持ちになっていた。
労作展一日目。所属している野球部の招待試合が午後にあるため、午前中のうちにみんなの作品を見てまわろうと思い朝一番に登校した。そうは言っても、やはり自分の作品の評価が気になった。僕の作品に「賞」の札が付いているのを見た時、思わずガッツポーズをした。
僕の作品は「モーツァルトのきらきら星変奏曲を参考に駅メロを編曲する」というものだ。僕は普通部に入学する前から音楽分野で労作することを決めていた。小さいころからピアノを習っている。すごく上手に弾けるということではないが、自分の持ち味を出せるのはピアノに関することだと思ったからだ。
四月から始めた慣れない電車通学の途中、乗換駅で流れる電車の発車メロディ、所謂「駅メロ」を聞くのが楽しみだった。僕は音鉄という訳ではないが昔から駅メロが好きだった。だから、駅メロを労作展のテーマに出来ないかとなんとなく思った。しかし、駅メロをただ弾くだけは面白みがない。それならば、短い駅メロを長い曲にしたら良いのではないかと考えた時に、モーツァルトのきらきら星変奏曲のことをふと思い出した。みんなが知っている「きらきら星」をモーツァルトは十二パターンにも編曲しているのだ。その曲を改めてじっくり聴いてみると「簡単なメロディがこんな風に壮大にアレンジされているんだ。」と驚いた。モーツァルトがアレンジしたいくつかのパターンを参考にして駅メロを編曲したらいいんじゃないかと思った時、僕なりにいい考えが浮かんだと思った。そうと決まったら「労作展計画表」はすらすらと書けた。
しかし、実際に労作が始まると「編曲なんてすぐに出来るんじゃないか。」と思ってしまっていた自分を悔やんだ。編曲をした経験なんて一回もなかったし、聴いた曲をすぐにピアノで弾くという「耳コピ」も出来ないし、コードなどの音楽の知識もない。では、そんな僕がどうやって編曲したというと、両方の原曲をピアノで弾きながら頭に浮かんできた案をひたすら弾くことを繰り返したのだ。気が付いたらピアノの前に五時間ぐらい座っていたときは自分でも驚いた。集中していたというより、やらざるを得ない焦燥感がそうさせたんだと思う。
「労作展音楽科要綱」の中に音楽科の鎌田先生が「音楽しよう」いう言葉を書かれていた。焦燥感に苛まれ、生みの苦しみを味わった末に編曲をようやく完成させたときは「よし、僕は音楽をした。」と思え、不思議な満足感に包まれた。
労作展二日目。音楽科労作展コンサートに僕も出演した。緊張はもちろんしたが、自分が編曲した曲を聴いて貰いたいという思いが勝ったのか、わくわくした気持ちで臨めた。
今回の労作では音楽理論のことを深く学べていないのが心残りなので、来年度、また音楽分野での労作に挑戦するならば、そういったところをもう少し丁寧に取り組みたいと思う。