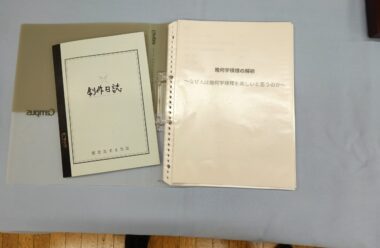数学科
労作の意義
3年R.K.君
僕は一年生では魚の解剖実験、二年生では植物分布調査と理科の生物分野に興味を持ち、労作展のテーマとした。そして、そのままの流れで三年生も理科にしようかと考えていたが、ふとあることを思い出したのだ。小学生の頃、幾何学模様のような図形を描くことが好きで、よく紙一面に描いていた。なぜ幾何学模様に惹かれたのか。これをテーマに労作展に臨もうと決めた。この時、数学科か美術科、どちらの視点で研究を進めようか迷ったが、図形や模様の規則性について解明したいと考え数学科にした。
手始めに図書館で借りてきた本のうち、岡本健太郎さんという数学者でありアーティストである方の本に興味を持った。Excelを使って図形を描くExcelアートについてのセミナーを開講されていたのを見つけ受講してみた。数式を当てはめると一瞬で美しい幾何学模様を描けることに感動し、その後数日Excelに格闘した。なんとなく自分でも描くことはできたが、思い通りに描くまで関数を理解しきれず挫折してしまった。
別の視点からのアプローチを探ろうと、代々木にあるイスラムのモスク(礼拝堂)に行ってみた。イスラム教の世界では幾何学模様が多く取り入れられており、実際に建物の天井や壁、家具などにもたくさんの幾何学模様が描かれていた。それらを見て、模様にも種類やパターンがあるように感じられ、文献にあたったところ、「平面群理論」という十七種類のパターンがあることを知った。模様は四つの基本移動だけで構成されており、その基本移動を組み合わせた十七種類の展開方法があるという理論である。僕はそれを自分なりに解析していくことにした。
オリジナルの基本モチーフを使った十七種類の法則の説明、実際に見たモスクの模様の分析、イスラム模様だけでは物足りず、同じような図柄で構成される日本古来の和柄の分析を行い、論文にまとめた。文化的背景に言及し数学から少し離れてしまった部分など反省はあるものの、自分自身の小さな疑問をきっかけに、未知の分野で活躍される方や新しい世界に出会い、当初考えていた以上の成果を得られたことに自分では満足している。
三年間の労作展を振り返ると、教科やテーマは異なるが、自分の足でサンプルを集め、細かく調べ、比較し考察する手法を共通して用いた。自分の興味に基づいて調べたり分析したりすることは没頭できる時間でもあったが、論理的に表現することには難しさも感じた。また思い通りにいかない場合には原点に立ち返ってみたり、様々な視点から物事を見ることの大切さにも気付かされた。三年間、向き合ったことで得られたこの経験をもって、労作の意義を知った気がする。